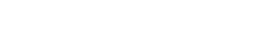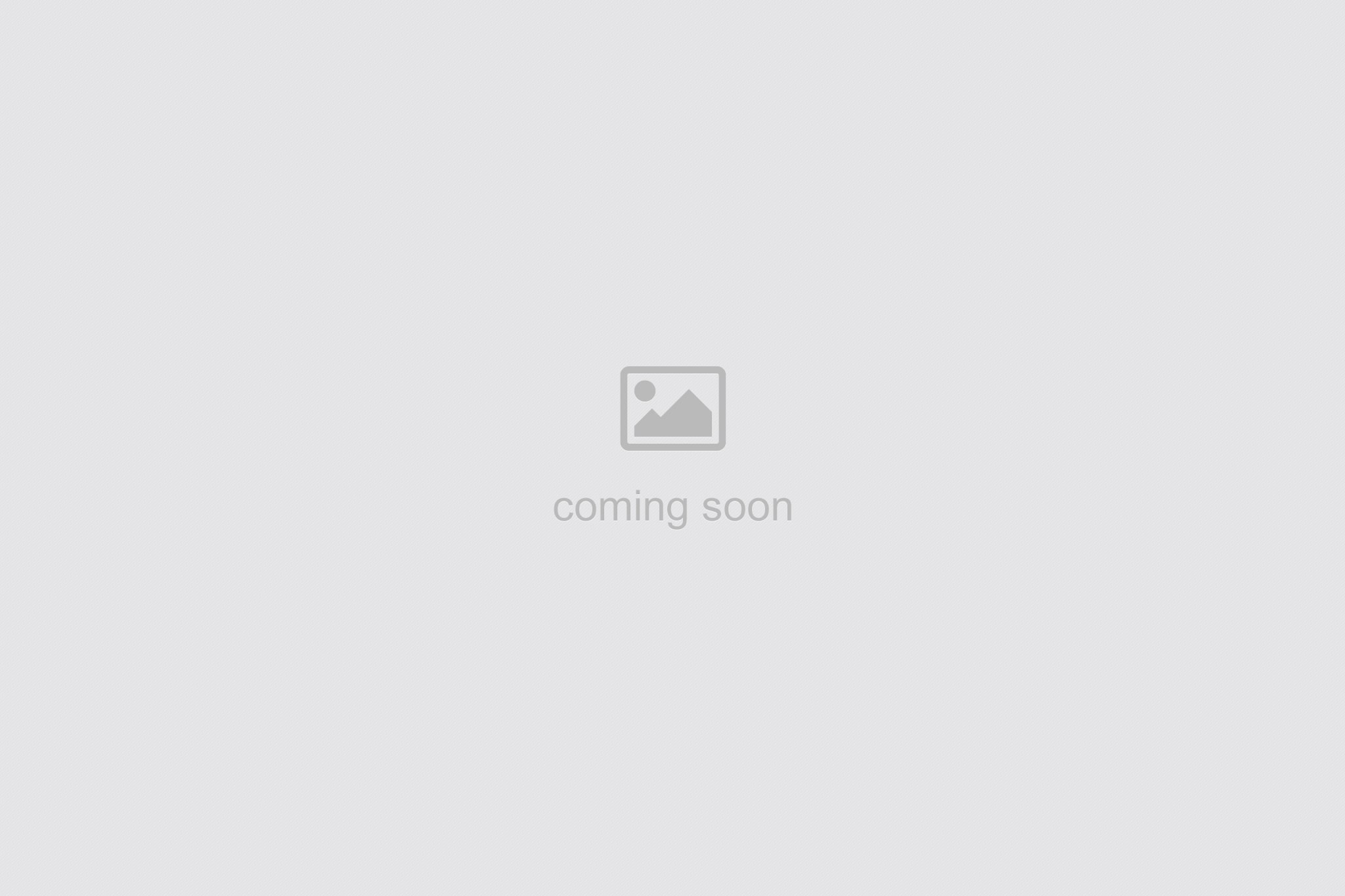令和三年葉月朔日歌合
歌合とは…
歌合とは、平安の昔より歌詠みを左右に分け、和歌の優劣を競った、清雅な競技です。
かつては雅な遊びに近いものでしたが、次第に歌詠みの矜持をかけた重いものとなります。
また、時代の変遷により、事前に題を出して歌を召し、実際に顔合わせすることのない形も多くなり、また時を超えて過去と現在の歌詠みによる和歌を番える『時代不合歌合』もあったのです。
鎌倉宮で御朱印を受けられた方々の心に、やさしく、うつくしい、『やまと言の葉』をご紹介したく、毎月二回、一日と十五日とに、古今の歌詠みたちによる秀歌と、当職の和歌とを番えています。
鎌倉宮第二十六代宮司 小岩裕一識
葉月朔日歌合
左
拾遺愚草 韻歌一二八首 夏
立ちのぼる 南の果てに 雲は有れど
照る日隈無き 頃の虚
権中納言定家
右
平成二十五癸巳歳 稲村百首
かゝる日も 有りきと告げよ 片瀬浜
星影照らす 夏の夜語り
大塔宮鎌倉宮 宮司 小岩裕一
葉月朔日の和歌
八月初旬、夏の暑さは盛りを迎えます。
先にも話した通り、王朝和歌の世界では
『真夏の暑さ』に正面から向き合う和歌は少ないのですが、ごく稀に詠まれているのが、掲出した定家の一首です。
もっとも、この和歌は「韻歌」といい、漢詩の韻を踏んだ漢字一字を読み込むという制約のもとに詠まれたもの、この一首は「虚(おおぞら)」という題を与えられて詠んだものです。
「虚」と言う一字を「おおぞら」と詠んだ定家の心には、どんな気持ちが込められていたのか、今となっては知る由もありません。
しかし、「みなみ」「雲」「おおぞら」などの言葉に、夏らしい情緒があふれている、不思議で貴重な「夏色」の一首です。
鎌倉宮第二十六代宮司 小岩裕一識
葉月望日歌合

葉月望日歌合
続古今和歌集 夏歌
夏山の 楢の葉そよぎ 吹く風に
入日涼しき ひぐらしの声
後鳥羽院御製
右
平成四壬申歳
ひぐらしの 声聞き初むる 夕べには
秋の色なる 風ぞ言問ふ
大塔宮鎌倉宮 宮司 小岩裕一
葉月望日の和歌
八月も半ばを迎えると、それまでの暑さと少しづつ雰囲気を変えながら、それでも夏はまだまだ続きます。
この頃になると私たち現代人の耳にも気になるのが「蝉の声」、中でも「ひぐらし」の声は別格の存在感を感じます。
王朝和歌の世界でも、「蝉の声」や「蝉の諸声(もろごえ、合唱のような声)」という言葉が頻出しています。
もっとも、それは「夏」だけではなく、「秋」の景物としても詠まれており、特に「ひぐらし」は独特の切なさを生む声が貴ばれ、多くの名歌が詠まれています。
掲出の一首は、歴代天皇中第一の歌詠みであられた後鳥羽院の御製です。
八百年も昔の歌ながら、今目の前に夏の風がそよぐのを見、目を閉じると「ひぐらし」の切ない調べが聞こえてきそうな、上質で瑞々しい臨場感のあふれる、至上の一首です。
鎌倉宮第二十六代宮司 小岩裕一識